連載 てくてく歩行学
川口俊太朗の
歩行学入門

川口 俊太朗 プロフィール
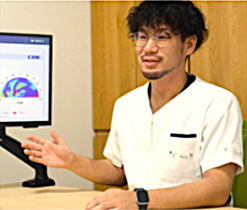 2019年 国際医療福祉大学大学院修士課程 修了。
2019年 国際医療福祉大学大学院修士課程 修了。
病院で勤務しながら専門分野における学会発表、論文を多数行っている。
現職:2014年苑田会ニューロリハビリテーション病院に入職
専門分野:歩行分析、下肢装具、経頭蓋磁気刺激、半側空間無視
3 健康寿命を延ばすために① フレイルとは?
年齢を重ねるにつれて、「最近なんだか疲れやすい」「筋力が落ちてきた」と感じることはありませんか? それ、もしかするとフレイルやサルコペニアのサインかもしれません。これらは高齢者の健康維持において重要なキーワードです。今回は、健康寿命を延ばすために知っておきたいこととして、フレイルの特徴やチェック方法についてご紹介します。
フレイルとは?
フレイルとは、加齢に伴い身体的・認知的・社会的な機能が低下し、健康な状態と要介護状態の中間に位置する状態のことを指します。フレイルが進行すると、転倒や認知機能の低下を引き起こし、最終的には要介護状態になるリスクが高まります。
1. 身体的フレイル
加齢や疾病により筋力、体力が低下し活動量が低下した状態。
フレイルの評価基準として、改訂日本語版CHS基準(J-CHS基準)をご紹介します。
| 項目 | 評価基準 |
|---|---|
| 体重減少 | 6か月で2kg以上の体重減少がある |
| 筋力低下 | 握力が男性28kg未満、女性18kg未満 |
| 疲労感 | この2週間、理由もなく疲れた感じがする |
| 歩行速度 | 通常歩行速度が秒速1.0m未満 |
| 身体活動 | ① 軽い運動・体操をしていますか? |
| ② 定期的な運動・スポーツをしていますか? | |
| ① ②の質問に対して、「週1回もしていない」と回答 |
改訂日本語版CHS基準(J-CHS基準)
・該当なし → 健常
・1~2項目に該当 → プレフレイル
・3項目以上に該当 → フレイルの可能性あり
2. 社会的フレイル
家族や友人・知人との交流機会が減少するなど、社会的に脆弱な状態です。以下の質問に回答してみてください。
Q1. 一人暮らしですか?(「はい」と回答した場合に該当)
Q2. あなたは、近所の方とどの程度つき合いをしていますか?(「3または4」と回答した場合に該当)
① お互い訪問し合う人がいる
② 立ち話をする程度の人がいる
③ あいさつをする程度の人がいる
④ つきあいはない
Q3. 次の地域活動に参加していますか?(いずれも「なし」と回答した場合に該当)
① 祭り・行事
② 自治会・町内会
③ サークル・自主グループ
④ 老人クラブ
⑤ ボランティア活動
⑥ その他
Q4. 現在の暮らしの状況を経済的に見てどう感じますか?(「1または2」と回答した場合に該当)
① 苦しい
② やや苦しい
③ ややゆとりがある
④ ゆとりがある
以上の回答が2~4項目以上該当すると「フレイル」、1項目該当「プレフレイル」、0項目「問題なし」と判定されます。
3. 精神・心理的フレイル
心理・精神的フレイルは、認知機能低下、うつ症状、それにアパシー(無気力・無関心)などの状態が含まれます。
精神・心理的フレイルは、一般的に標準化されている判断基準はありません。
フレイルの有病率は高く、80歳以上では30%以上該当すると言われています。他人事と思わず是非チェックしてみてください。
2 加齢による歩行の変化
加齢により関節可動域減少、筋力・バランス能力などが低下していくことが知られています。これらの変化は歩行能力の低下を招き、活動範囲の狭小化や転倒のリスクを増加させます。世界保健機関(WHO)によると、65歳以上の高齢者の約3人に1人が毎年少なくとも1回は転倒すると報告されています。また、転倒のリスクは加齢とともに増加し、80歳以上では約半数が転倒を経験するとされています。
また多くの高齢者は何らかの疾病を有していることが多いため、加齢による変化と疾病による両方の影響により歩容が悪化します。そのため、歩行の特徴を理解し予防することが重要になります。
転倒による影響
- 骨折のリスク:転倒によって特に大腿骨頸部骨折や手首の骨折が多く発生します。
- 入院や要介護のリスク:転倒による怪我は、長期入院や介護が必要な状態につながることが多くなります。
- 心理的影響:転倒経験者は再び転倒することを恐れ、活動量が低下し、筋力やバランス能力が低下する悪循環に陥ることがあります。
定期的に歩くことは重要であり、身体機能を維持・向上させるだけでなく心疾患・認知機能障害のリスクを低下させ、精神的健康の改善につながります。
今回は、特徴的な加齢に伴う歩容の変化をピックアップします。

体幹の前後傾
- 歩幅の低下
- 歩行速度が遅い
- つまずきの増加
- 股関節、膝関節、足関節の運動範囲が減少
- 歩隔(歩行中の両足の幅)の増加
- 体幹動揺(歩行中に体が左右に揺れる)
上記の特徴が複数当てはまっている方は、要注意です。心配な方は、近くの医療機関や近隣で行っている予防教室などに参加し歩きをチェックしてもらいましょう!
1 正常歩行 〜健康的な歩き方とは?〜
歩くことは日常の基本動作ですが、意識せずにいると歩行のバランスが崩れ、異常歩行につながることがあります。ここでは、正常な歩行の特徴について詳しく見ていきましょう。
正しい歩き方の4つのポイント
①姿勢コントロール
- 背筋をまっすぐにし、直立で立つ。
- 重心は左右前後に偏らないようにし、身体の中心に位置するように意識する。
- 歩いている時は、視線を前に向け直立姿勢を維持し、体のバランスを保つことを意識する
壁に背中をつけて立つと背筋がまっすぐかどうかわかりやすのでチェックしてみよう。

②ロッカーファンクション
- しっかり膝を伸ばし踵から着地しましょう。これは、膝や股関節への衝撃を軽減します。また前方への重心移動がスムーズにあり、反対足の振り出しがしやすくなります。
- 足を振り出すときはつま先で地面を蹴る。
足を出す際に、つま先で地面を蹴ることで前方への推進力が生まれスムーズな歩行に繋がります。
③リズミカルで反復的なパターン
- 歩行には一定のリズムがあり、立脚期(足が地面についている時間)と遊脚期(足が浮いている時間)が交互に繰り返されます。
- このサイクルがスムーズであるほど、歩行の流動性が高まります。
転倒のリスクが高い人ほどリズムが悪く、左右非対称な歩きになります。歩行時には、意識してリズミカルに歩くように心がけましょう。
④地形への適応力
- 正常な歩行では、さまざまな地形(平坦な道、坂道、凹凸のある道など)に適応する能力が必要。
- 環境に合わせて足の動きを調整し、安全に歩くことが重要です。
このように、正常歩行は複数の要素が組み合わさって成り立っています。自分の歩行をチェックし、バランスや姿勢を意識することで、健康的な歩き方を維持しましょう!